◇今の職場、「自分に合っている」と感じる人はどのくらいいるだろうか?
今、自身が勤めている会社を「自分に合った職場」だと感じている人は、どの程度いるだろうか。社会人であれば誰でも一度は考えたことがあるのではなかろうか。
もちろん、現在の職場が自分に合っていると感じている人もいるだろう。しかし、そうではないと感じている人もまた多くいるはず。今は時代が変わり、転職が当たり前になりつつあるが、一方で新卒重視の採用や一つの企業で長く働くことが良いとされる風潮は、まだまだ根強く残っているのもまた事実。
それゆえ、「一度入った会社だから…」「せっかく新卒で入社したから…」という理由で、理不尽な扱いや様々なハラスメントに耐えながら働き続けている人も、少なくないのではないだろうか。
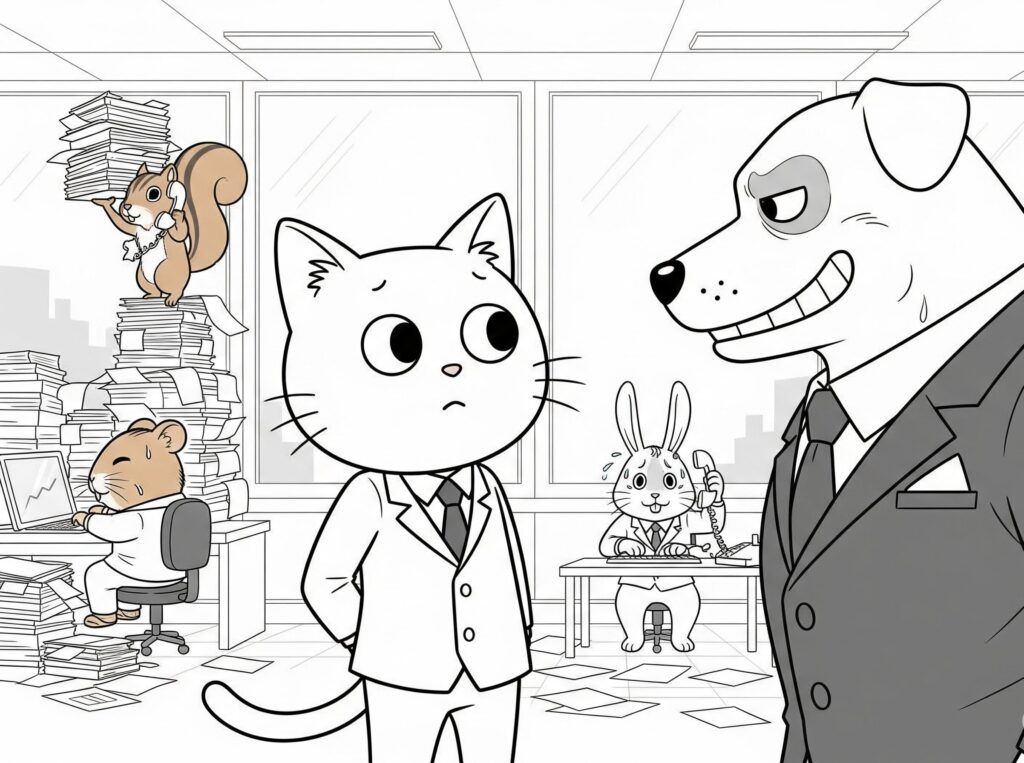
◇新卒が陥りやすい「ブラック企業の錯覚」
特に新卒の時点では就職するまで実態がわからず、入社してからも理不尽なことがあってもそれが当たり前だと錯覚してしまう場合もある。
そしてある日、ブラック企業だと気づいても、先程述べた「一度入った会社だから…」「せっかく新卒で入社したから…」という理由で辞め時や転職の機会を失い、惰性で働く…という負のスパイラルに陥るケースも少なくない。

◇「自分に合った職場」探しはなぜ難しいのか?
これは個人的な見解だが、「自分に合った職場」に出会うことは非常に難しいと思っている。ここ数年で転職サイトが増え、CMなどの広告を目にする機会が増えたことも、その難しさを物語っているように感じる。なぜかというと、例えば給料が良く、残業も無く、設備投資も行っており有給休暇も取りやすい職場があったとしても、直属の上司がパワハラをするような人間であれば待遇面は良くても一気にブラック企業認定してしまうのではないだろうか。
自分の理想の中で何か一つでも欠けてしまうと「自分には合ってない」と感じてしまう。
また、隣の芝生は青く見えるもので、実際に会社を辞めた後に「やっぱり前の会社のほうが良かった」なんて話をする人も少なくない。
実際、私も一度転勤で他県の支店に在籍したことがあるが、そこはそこで色々と大変だった。どちらが良いか一概には言えないが、少なくともサラリーマンとして収入を得る上では、ある程度の理不尽な苦労が伴うことは、その時に理解した。他の会社を経験したことがある人(転勤・出向・転職など)であれば、そのことに気づいた人も多くいるだろう。完全なブラック企業ではないものの、改善する余地がある、世代交代や改革が必要だと感じている人も少なくないはずだ。
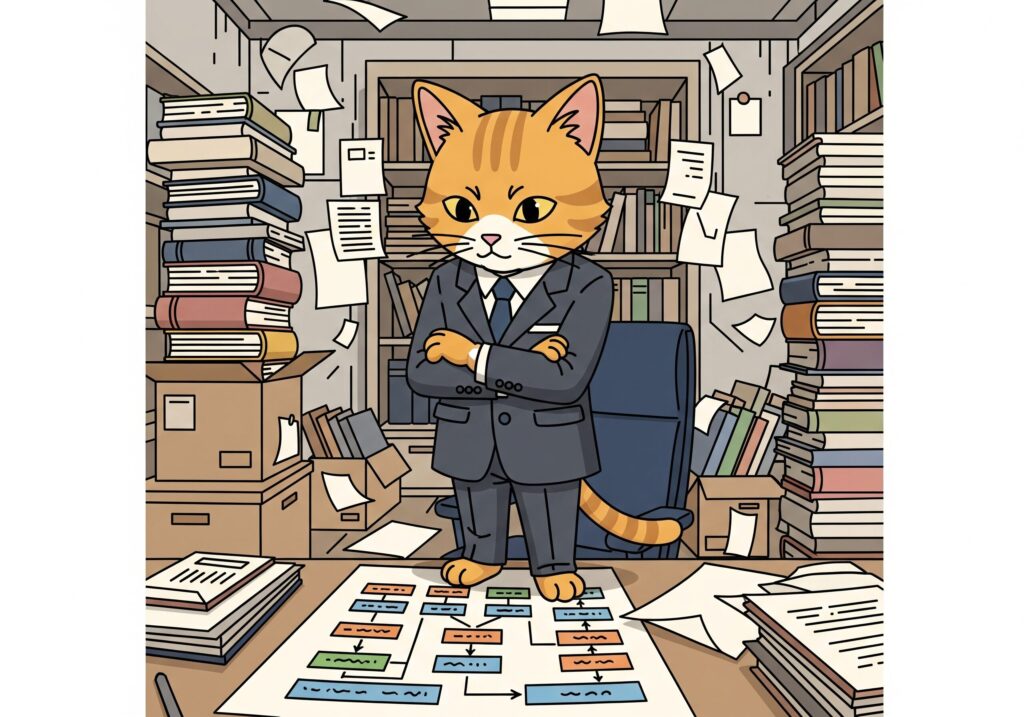
◇会社に残る選択:現状打破のための思考法
だからといって、ブラック企業で我慢して働き続ける必要は全く無い。働いていれば誰でも1度は「会社を辞めたい」「転職したい」と考えることがあるだろう。私もそう思ったことは何度もあるが、一方で十数年勤めた会社を辞めるのも、少し躊躇してしまう…という思いがあるのも事実。
恐らくその狭間で揺れている人たちはたくさんいると思う。
様々な選択肢がある中で、もちろん会社を辞めて転職することも良いことだと思う。
ただここでは会社に残る選択をした際に、どのような対処・対応をしていけば良いか、個人的な見解を述べたいと思う。
特に、以下のような思いを抱えている方には、ぜひ読んでいただきたい。
・「せっかく何年も勤めている会社だから、なんとかしたい」
・「嫌な奴はいるけれど、そいつのせいで会社を辞めたくない」
・「経営陣だけ無能で、他の従業員はいい人ばかりなので、この会社をなんとかしたい」
・「ある程度の勤続年数がある、または役職に就いているものの、辞めたくはないが現状を
なんとかしたい」
・「クソ上司に一矢報いたい」
現実的な考え方として、「自分に合った職場」を探す前に、まずは今の状況を整理することが重要である。その上で、「自分に合った職場」という考え方から「今の職場を自分に合ったものにするためにはどのような行動を取るか」という考え方へシフトする必要がある。

◇問題を明確化し、ゴールを設定する3ステップ
まずは自分の置かれた状況を整理してみよう。
1.はじめに、今の職場に対して抱いている問題(不満)を明確化する。
※例:待遇面、環境面、人間関係など
2.次に、どうすれば自分が過ごしやすい環境になるか、ゴールを明確化する。
※例:問題(不満)が上司からのパワハラだった場合、ゴールはパワハラを無くす、
自分または上司が部署を異動すること等
3.最後に、問題(不満)とゴールの溝(ギャップ)を埋めるためにはどのような解決策があるか、どのような行動が必要かを明確化する。
※例:上司の上司や労働基準監督署へパワハラの相談をする、または別の人間から
パワハラ被害の内容を伝えてもらう、異動願を出す等
考え方としては、上記のようなフローが最適だと思う。大切なのは、「どうすれば現状を打破できるかを考え、行動する」ということである。そのためには、目的をはっきりさせなければならない。
上記に加え、「目的→手段→行動→検証」の流れを1つのサイクルとして考え、行動することが重要だ。
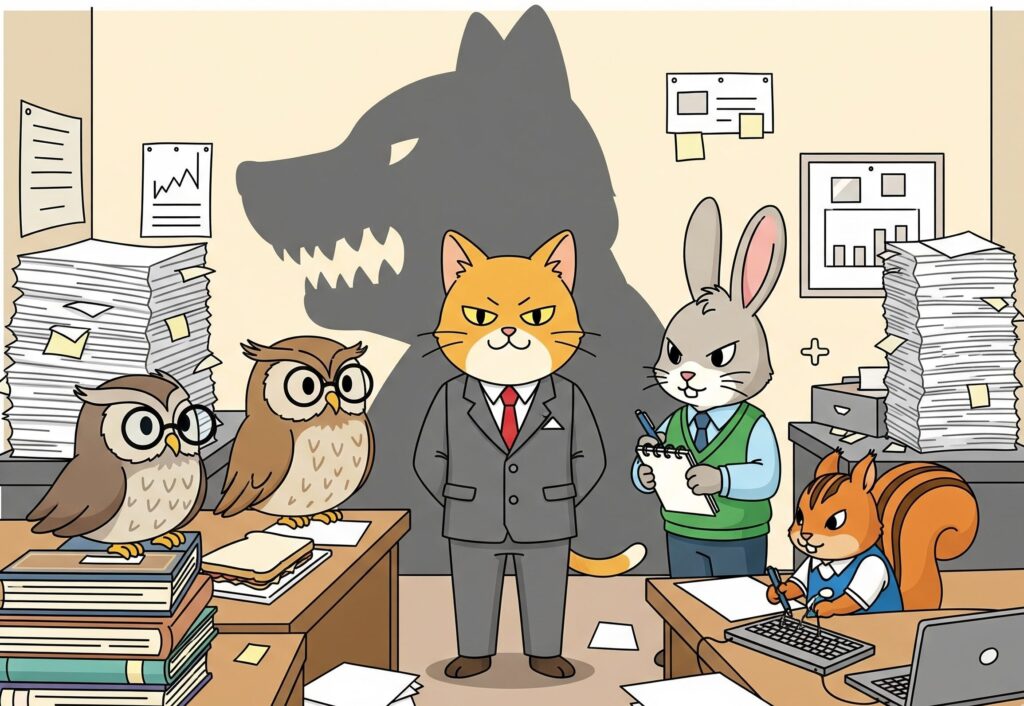
◇一人で抱え込まず、仲間を作る重要性
一人で行動するには限界があるため、少人数で良いので仲間を作ることも大切だ。まずは信頼できる人を探し、少しずつ状況を共有していく。ただし、ここで気をつけなければならないポイントがある。それは、味方であっても全てを話すのは避けた方が良い、ということだ。なぜなら、「ここまでは話してもいいが、これ以上は秘密にしておきたい」という境界線が、必ず出てくるからだ。秘密にしたい、あるいはまだ公開したくない情報は、誰にも話さない方が賢明だ。この境界線は人によって異なるため、うっかり口外されてしまう可能性も考慮しておく必要がある。
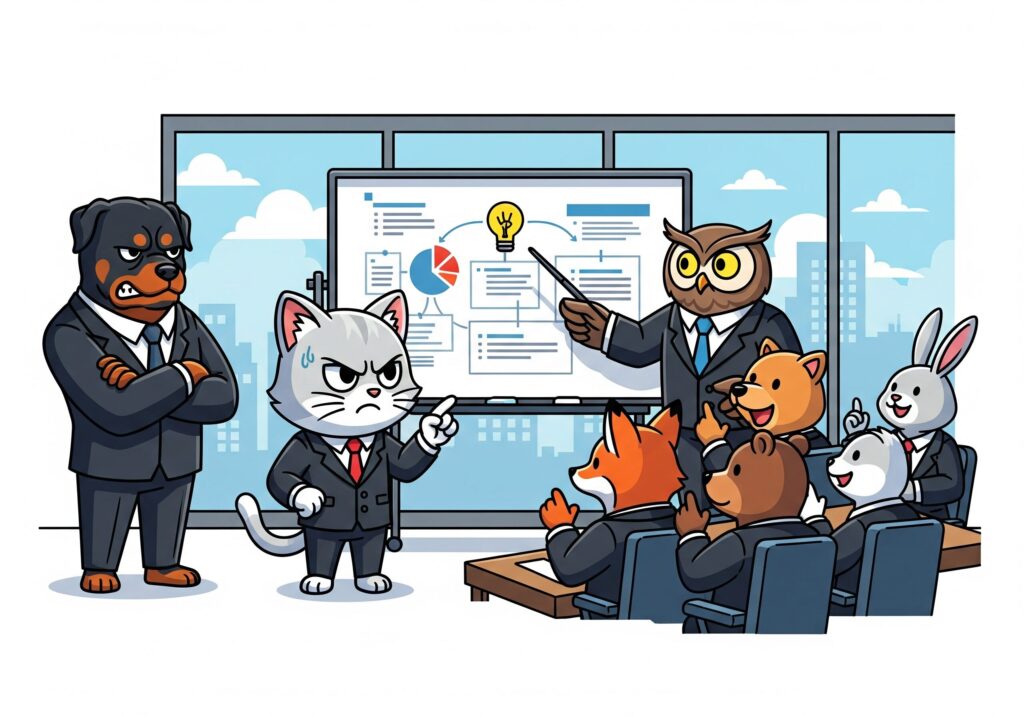
◇「誰が言ったか」が影響する現実と、長期的な視点
物事を進めるにあたっては、自身が行動すべきことと、他者に協力を仰ぐこと(行動を促すこと)を分けて考える必要がある。例えば、役職がない、あるいは実績がまだ少ない社員が正論を述べたとしても、上司や上層部は、自分たちに都合が悪い情報であればあるほど、以下のような言葉を盾に押し切ってくる可能性がある。
(「まだ若いのに」「経験が少ないのに」「まだ入社して数年のくせに…」など)
私もサラリーマンとして働いているが、「このミーティングは無駄じゃないか?」「この資料は毎月作っているけれど、誰が使っているのだろう?」といった様々な疑問を抱くことがある。それを上司に話しても、「伝統だから」「昔からやっているから」と言われ、終いには理不尽に怒鳴られて終わり…と、全く話を聞き入れてもらえなかった、という経験も多くある。
その対処法として、自分の代わりに意見を代弁してくれる人間を探す必要がある。厳しい現実だが、同じ内容であっても人は「誰が言ったか」によって、随分と印象が変わってくるものである。たとえ自分の意見が通らずとも、他の人が同じ意見を述べたことで解決するなら、それで問題ないと割り切る心持ちが大切だ。正直、『自分の意見なのに…』と思うことは多々あるが、ここで目的を見失ってはいけない。自分が目立ったり、自己顕示欲を満たすことが目的ではないため、しっかりと長期的な視点を持つことが重要だ。少なくとも、あなたの意見に賛同してくれた人は、あなたに一目置いてくれるようになるだろう。戦況はすぐには変わらないため、少なくとも数ヶ月から数年のスパンで、一つずつ丁寧に計画を練ることをおすすめする。

◇冷静な計画と行動が未来を変える
繰り返しになるが、重要なのは問題をいかに解決していくか、ということだ。
長い人生、そして長い社会人生活の中で、会社を「自分に合った会社に変える」ためには、感情的にならず、冷静に計画を練って行動することが何よりも大切である。




コメント